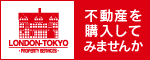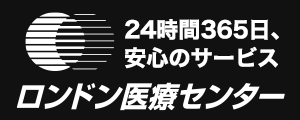国民国家と移民
英国におけるイスラム系・インド系住民、フランスにおけるマグレバン(北アフリカの元フランス植民地出身者)、ドイツにおけるトルコ人、南欧諸国における東欧の若者と、欧州では移民が今住んでいる社会に「同化」できないことが大きな社会問題になっている。言い換えれば低賃金労働への従事、生活水準の低さ、言語の違い、教育水準の低さ、宗教の違い、これらを原因とする犯罪の多さが問題視されている。
一方で移民からみれば旧宗主国に対する劣等感を底流に、低賃金で働かせた上に景気が悪化すると移民制限とは虫が良すぎる、と大きな不満がある。これが英国にイスラム原理主義が入り込む余地であったし、パリ郊外での暴動の原因であり、逆に大陸などで移民排斥を掲げる右翼、国粋主義が躍進する土壌となっている。
歴史的に見れば、欧州では神聖ローマなどの各帝国内でのユダヤ人問題も同根と思う。現在に繋がる起源としては、帝国主義が崩壊した後に国民国家が国民をまとめ上げるに際し、民族アイデンティティーを確立していく過程で少数民族を慰撫と敵視で利用したことにある。つまり言文一致運動、マスメディアの誕生、義務教育等々によって国語と歴史を国民に共有させ、金融と貿易により経済圏を統一した。その過程でついて来られなかった少数民族を追い出し、ついて来られた層を国民として取り込んだ。この問題を歴史的に正面から受け止め、社会的な努力を続けてきた国は米国である。
米国の公民権運動
若い移民の国である米国の国内史は、アングロサクソンや他の欧州移民そして黒人の同化、最近では原住民インディアンについての評価の見直しなど移民問題を軸にうねっている。中でも鉄道内での白人・黒人分離車両を「分離すれど平等として合憲」と判断した1896年の最高裁判決を覆し、白人・黒人を分離した学校を違憲とした1954年のブラウン対教育委員会裁判をきっかけとして盛り上がったキング牧師の公民権運動は、他国に例がない。法的権利の平等から、経済的に恵まれない黒人に一定の大学入学枠を優先的に認めるなど、州や国家が積極的な配慮(affirmative action)を取るようになったことは画期的であった。
ただ配慮にも限界がある。結局、混血が進めば一定の同化はあるものの、資本主義の下では所得格差、教育格差は容易に埋まらないし、法の下の実質的な平等の確保による行き過ぎた積極的配慮には反動もみられる。保守が区別、分住を肯定する一方、自由を支持するリベラル派は区別を禁止し、混住とさらには一定の積極的配慮を支持する。
米国の共和、民主両党に保守とリベラルの立場の人がいる。黒人オバマ候補の「米国は1つ」という訴えも、その出自のみならず、米国の経済的苦境に対して具体的、そして積極的に不平等を是正する政策を語れば失点になりかねないという状況から生まれたのであろう。
英国の場合とカンタベリー大主教
英国は帝国主義時代に多数の植民地を持ったが、常に植民者であり、多数の英国人が現地に同化することはなかった。英国内でも植民地エリートを中心に留学を認めたのみで、米国のような規模での移民流入はない。植民地における独立の混乱で亡命したインド系と一部アフリカ系の2代目、3代目が教育を受け中産階級に進出しているが、分住しており、米国のような激しい法律、政治闘争もない。しかし、いまやグローバリゼーション、言い換えれば国民国家から帝国主義の復活への新展開が、英国に史上初めての経験を強いているのではないか。イスラム原理主義が入るに及び、問題は政治社会化した。カンタベリー大主教が、英国でイスラム法(シャリーア)のイスラム社会への部分的適用を主張したことは記憶に新しい。
こうした分住の固定化は、米国ではヒスパニックで問題になっている。これは法の下の平等、法の支配という権利章典以来の英国法史と真っ向から衝突する。大主教や労働党が支持してきたマイノリティの社会参加のための分住支持は、米国なら保守の主張に当たる。英国保守党のキャメロン党首は区別禁止という、極めてリベラルな主張の持ち主だ。英国が植民地でしてきたこと、パレスチナやアフガニスタンでしてきたことを考えると、歴史は移民同化という古い問題を逆に英国本国で問い返してきた。キャメロン党首は経済政策ではブラウン首相と差異を出すことは難しいが、こういう分野でこそ真骨頂が問われる。政権奪取の契機とさえなるべき問題だと思うが、さてイートン、オックスフォード卒のエリートにそれができるか。
(2008年4月13日脱稿)



 在留届は提出しましたか?
在留届は提出しましたか?

 英国経済の強さと同時に、そのアキレス
腱となるのがロンドンである。図1を見ると、
ここ10年で英国経済に占めるロンドン、そしてロンドンと密接に関係がある南東部の経済活動(付加価値)のウエイトが上昇していることが分かる。足許ではロンドンが約17%、南東部を合わせると3割強になる。
英国経済の強さと同時に、そのアキレス
腱となるのがロンドンである。図1を見ると、
ここ10年で英国経済に占めるロンドン、そしてロンドンと密接に関係がある南東部の経済活動(付加価値)のウエイトが上昇していることが分かる。足許ではロンドンが約17%、南東部を合わせると3割強になる。