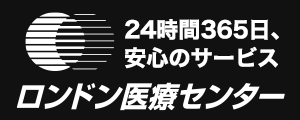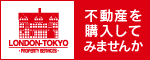スーダンの間隙
エジプトの南、アフリカ大陸で最大の面積を持つ国スーダンの原油の半分以上は、中国向けに輸出されている。一方の中国はスーダンに対して人的、金銭的に多大な投資を行っている。これまでも中国は、石油プラント、パイプライン、レアメタル鉱山などに中国国営企業や数万人の労働者を派遣して、経済面での援助を行いつつ、武器輸出を通して政治的な関与を強めてきた。特に道路、橋梁(きょうりょう)などへの投資に重点を置くスーダンへの関与の方式は、「インフラを握るものは天下を制する」という意味で、アフリカとの関係構築の模範とされているようだ。
石油資源やレアメタルなどの鉱山資源を多く有するスーダンはもともと英国の植民地であり、英国が同地の利権に深く関与していた。しかし、例によって英国は、北部アラブ系住民(主にイスラム教徒)と南部アフリカ系住民(主に黒人で、キリスト教徒または土着宗教の教徒)のどちらにもいい顔をする分割統治を行い、1956年の独立直後から内戦が勃発。イスラム教徒やアラブ系を中心とする政権と、これに対する南部のデインカ人を中心とする反イスラム勢力との反目や実質的な分割統治、さらには政権内部での派閥抗争の2点が内戦の基本構造になっている。西部ダルフール地区での紛争はその応用問題で、政府と政権を握るアラブ系住民らによる、反政府ゲリラや非アラブ系住民への迫害、隣国チャドへの難民が問題となっている。
キリスト教をバックとする西欧諸国や国連は、スーダン政府を人道的見地から非難し、バシール大統領には戦犯容疑で国際刑事裁判所から逮捕状が出ている。西欧メジャーがスーダンに投資しにくくなったこの間隙を、中国は見逃していない。ナイル川の橋梁建設を日本に代わって受注し、ここを橋頭堡(きょうとうほ)として、資源を中心とする開発に食い込んできた。
非人道行為を行おうが、行うまいが、中国にとって役に立つ政府であれば援助するという、鄧小平の「黒い猫でも白い猫でもねずみを取る猫は良い猫だ」という主義を西欧諸国は批判しているのだが、現実のスーダン経済は、中国の独檀場になっている。グローバリゼーションの下、資源囲い込みにかかる欧米と中国の代理戦争となっているアフリカでの陣取り合戦の一例がここにある。
これからのスーダン
ダルフール地域からの難民流入を巡り対立していたスーダンとチャドが、双方の反政府勢力対応で歩み寄りつつあり、ダルフールにつかの間の和平が来る兆しはある。しかし南北の対立は根が深く、いずれ北スーダン、南スーダンに分国し、緩やかな国家連合体になるとの観測が根強い。ここに必ず、石油やレアメタルに関する利権を持つ欧米や中国企業、さらにはその背後にいる政府が介入することは、確実である。北を中国、南を欧米が取るという構図になると思われるが、果たして、それで解決と考えていいのかどうか。
特に中国にとっては、中国製の武器を有してアフリカ最強といわれるスーダン軍が南部を抑えている現況が好都合なはずで、現状維持を狙ってくると考えられる。中米対立の観点からも、スーダンは既に火がついているだけに、パワー・ポリティクスの展開を読むべき局面である。
日本人の活躍と日本政府
さて、わが日本はスーダンで何をしているのか。NPO法人ロシナンテスが一人気を吐いている。代表の川原医師が、無医村に医療センターを展開し、井戸掘り、学校など多面的な活動を展開しておられる。しかも、サービスの提供は無料ではない。小額でも支払いを受けることにより、経済的な自立を促しつつ、スーダン人の信頼を勝ち得ている。
全く姿の見えないのが、日本政府である。パワー・ポリティクスに参加するでもなし、ロシナンテスについて、寄付行為などに税制上の優遇措置を講じるでもなし。川原医師によれば、スーダン人は、本音を言うと、中国の露骨な資源取りを愉快には思っていないらしい。むしろ、中国製に比べてはるかに壊れにくい日本製の車そして電化製品を欲しがり、またそうした日本製品の影響で随分と日本のイメージは良いのだという。トヨタ、日産、ホンダ、SONY、パナソニック、YAMAHAなどの製品と川原医師の活躍は、確かにスーダンの支持を受けているのである。日本政府にとっては、無策による怪我の功名というべきか。
それなら、いっそ何もせず、川原医師や日本企業の活動への減税などの側面支援に徹するのが正解であろう。
(2010年3月1日脱稿)



 在留届は提出しましたか?
在留届は提出しましたか?