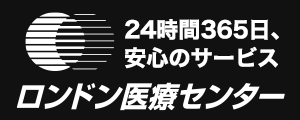リオデジャネイロの勝利
ロンドン大会の次に行われることになる、2016年のオリンピック開催地決定までの過程を報じる中継を見ていた。1回目の投票でシカゴが落ちたとき、リオデジャネイロの勝ちが決まったと思った。
勝因は、「南米大陸での初めての開催」これだけである。BRICSの経済台頭がもちろん背景にはあるが、それでも「南米大陸初」というテーマは、他の3都市に比べるとはるかに明快だ。この明快さこそが勝因だった。何の主張もない米国のシカゴや「悲願」と言うだけのスペインのマドリッドに比べると、東京が掲げた「環境」というテーマは時代に合っていたように思う。だが、まだまだ抽象的だった。ロンドンだって、4年前に「環境」ということを言っていた。それ以上に具体的なコンセプトを日本が示したとは言いがたい。
日本の製品が世界中に輸出され、日本国自体が、TOYOTA、NISSAN、HONDA、SONY、PANASONIC、FANACといった記号が象徴するもの、つまり「便利」「壊れにくい」「機能美」で認知されている。今後はこれらの点に加えて、利用者の暮らしや生活環境をいかに育むかをより意識した製品作りや販売活動を実践する必要があるというのは、もう日本企業の常識になっている。それをどうして、もっと具体的に発信しなかったのか。石原都知事の「(国際政治における学ぶべき)力学があった」、猪瀬副知事の「プレゼンは良かった。ハグし合うような国際オリンピック委員会の委員との人間関係が難しい」といった発言を聞いていると、その程度の認識なら負けるな、と思った。
「環境」とは何か
「環境に良い」ということを付加価値率の向上(相対的に少ない投入原単位による相対的に多い生産量の確保)と捉えると、ほとんどの経済活動は「環境に良い」ことを目指していることになり、企業活動そのものの紹介と何ら変わらなくなる。また消灯、コピー用紙節約など何らかの活動をやめることにより投入原単位を減らすことを「環境に良い」と捉えることも可能であるが、そうなると今度は製造業における不良品減少のためのクオリティー・コントロール(QC)活動との区別が難しい。
次に、石油や石炭に変わる代替エネルギーの開発や利用については、化石燃料を減らすことによる二酸化炭素(CO2)排出量削減には寄与するが、他の資源利用や影響などを考えないと、「トータルで環境に良い」か否かは何とも言えなくなる。原子力は、日本の再処理施設の不調によるコスト増加や、故障でも起きたときのインパクトの大きさまで考えるとどうなのか。太陽光ももっともっとコストダウンやエネルギー効率の引き上げがないと、CO2は削減されるが、社会全体としては非効率である。
CO2の削減や汚染土壌の浄化の義務化は、社会的コストを企業や家計が負債として負うことを明確化することで、負担者の行動を変えようとするものである。その変化は興味深いが、しかしながらコストの分配が起こることで、中長期で技術や市場によってこうしたコストを削減していける可能性が出てくるかどうかについては何とも言えない。またC O2削減量の人為配分は、配分者に情報取得の権限を含む大きな権力を与える危険がある。こう考えてくると残りそうなのは、「捨てられていたゴミを再利用する」という従来のリサイクルが、人間が、人間以外の地球環境に対して与える負荷を技術により減らすことで地球の維持・持続に寄与するという意味で、狭義の「環境」のテーマとして残りそうだ。
具体案と行動が必要
いずれにしても、東京は「環境」というコンセプトをもっと煮詰め、それを具体的に提示する必要があった。それが戦略というものだろう。オバマ米大統領も「好きなシカゴ、自分の育ったシカゴでオリンピックを観たい」とはお粗末につきる。こうなると「核のない世界」という理想すら、言ってみただけという感じに色褪せてしまう。鳩山首相の演説も然りである。言うだけなら誰でもできるのだ。政治家は、構想力を持って、コンセプトを明快にし、それを具体的な形で示し、実現してこそ評価される。このままでは、オバマ、鳩山とも中国にしてやられる。いや、その前に支持率が落ちていくのは時間の問題ではないかという危惧を持った次第である。もちろん環境という観点から見ると、オリンピックはそもそも必要なのか? という疑問も当然なので、英国人好みに結構シニカルにもプレゼン出来たと思うのだが。
(2009年10月4日脱稿)



 在留届は提出しましたか?
在留届は提出しましたか?