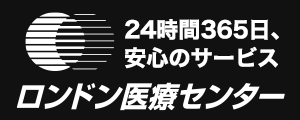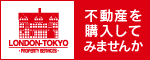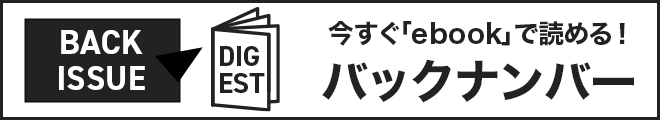スターマー首相、防衛費増額へ
ウクライナへの派兵も検討米政権「欧州のことは欧州で」
ロシアによる全面侵攻で始まったウクライナ戦争は、2月24日で丸3年となりました。ウクライナの戦死者は約7万人、ロシアは9万5000人と推定されています。翌25日、キア・スターマー首相はこの戦争によって「全てが変わった」と述べ、2027年までに防衛費(Defence Budget)を国内総生産(GDP)の2.5パーセントにまで増加させる計画を発表しました。30年までの達成目標の前倒しです。昨年の防衛費はGDP比2.3パーセントにあたる539億ポンド(約10兆円)でした。その数日前には英紙「テレグラフ」に寄稿し、戦闘終結後、ロシアの再侵略を防ぐ「安全の保証」としてウクライナへの英地上部隊の派遣を前向きに検討する意向を示しました。首相が派兵の検討を明言するのはこれが初めてです。欧州では今、「防衛費増額」そして「平和維持隊の派遣」がホット・トピックになってきました。
そのきっかけとなったのは、トランプ米政権による「欧州の戦争は欧州で片づけてほしい」と言わんばかりの一連の方針です。ウクライナへの人道、財政、武器供与などの支援では、もともとはソ連に対抗するために生まれた軍事同盟「北大西洋条約機構」(NATO)や欧州連合(EU)の加盟国が中心となってきましたが、なかでも支援規模がダントツなのはNATOで大きな存在感を持つ米国です。2月中旬、米政権はほかのNATO加盟国に対し改めて防衛費の大幅増額を求めるとともに、停戦後の安全保障は「有能な欧州軍と非欧州軍」が提供するべきとして米軍の関与を否定しました。欧州各国は米国抜きで対ロシアの防衛体制を担わざるを得ない状況に追い込まれました。
さて、では2.5パーセントで十分なのでしょうか? 英国の防衛費は1950年代半ばにはGDP比7パーセントほどでしたが、冷戦終結を経て90年代末以降は2パーセント前後まで落ち、防衛体制は削減、縮小に見舞われてきました。スターマー首相は次の総選挙がある2029年にはGDP比3パーセントまで増やす可能性にも言及していますが、この数字でも対ロシアの抑止策として「最低限の金額」に達するだけ、と見る専門家もいます。
一方、戦闘終結後にロシアとウクライナの国境付近への配備が想定される平和維持隊ですが、元陸軍参謀総長リチャード・ダナット氏はBBCに対し、英軍は「あまりに疲弊している」ため、今後ウクライナでどのような平和維持活の先頭に立つこともあり得ないと話しています。「人員的にも、軍事力、装備的にも無理だ」。平和維持隊への動員数は5万~10万人と推定されており、ダナット氏の見立てでは、「もし英国が地上軍1万人を派遣する場合、6カ月交代制で回していくとすると、3万~4万人を派遣兵及び予備兵として確保する必要がある。そんな余裕はないだろう」。防衛省によると、昨年10月時点で英国の正規軍の人員は海軍・海兵隊が約3万1000人、陸軍が約7万4000人、空軍が約3万7000人。英国はウクライナにすでに128億ポンド(約2兆4400億円)の支援を提供しており、毎年30億ポンド(約5720億円)の軍事支援を必要な限り行うことを確約しています。約5万人のウクライナ兵にも英国で軍事訓練を受けさせていますし、地上軍の派遣は対ウクライナ支援をさらに一歩前進させたものともいえるでしょう。
いくつもの疑問が湧いてきます。まずGDP比2.5パーセントは必要十分な規模なのか、人員は足りるのか? また軍事増強の資金を確保するため、対外援助予算を大幅削減することになったのですが、影響を受ける慈善団体から怒りの声が上がりました。米国への依存から脱却するため、英国を含むNATO加盟国は防衛費増大にやっきです。でも、防衛費増大化の傾向が強まる世界は人々に幸福をもたらすでしょうか。脅威を弱体化させる試みも必要では? 皆さんはどう思われますか。
Defence Budget (防衛費)
国の防衛力を整備し維持するための費用。32カ国で構成される「北大西洋条約機構」(NATO)は加盟国に対し防衛費を国内総生産(GDP)の2パーセントにするよう求めている。昨年時点で23カ国が達成した。最多はポーランドで4.12パーセント。今年1月、トランプ米政権は加盟国に対GDP比5パーセントまで増額させるべきと述べた。

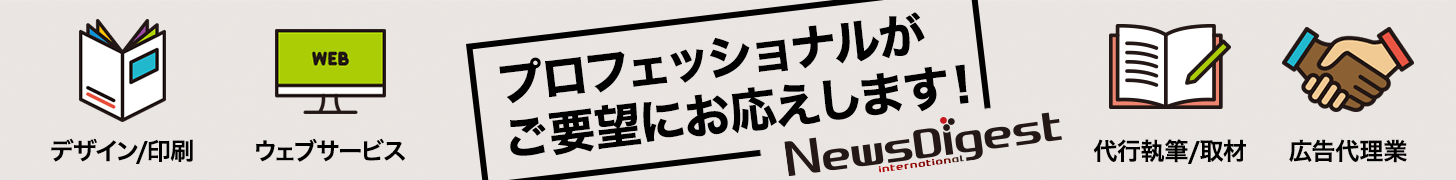

 在留届は提出しましたか?
在留届は提出しましたか?
 小林恭子 Ginko Kobayashi
在英ジャーナリスト。読売新聞の英字日刊紙「デイリー・ヨミウリ(現ジャパン・ニュース)」の記者・編集者を経て、2002年に来英。英国を始めとした欧州のメディア事情、政治、経済、社会現象を複数の媒体に寄稿。著書に
小林恭子 Ginko Kobayashi
在英ジャーナリスト。読売新聞の英字日刊紙「デイリー・ヨミウリ(現ジャパン・ニュース)」の記者・編集者を経て、2002年に来英。英国を始めとした欧州のメディア事情、政治、経済、社会現象を複数の媒体に寄稿。著書に