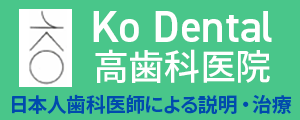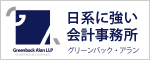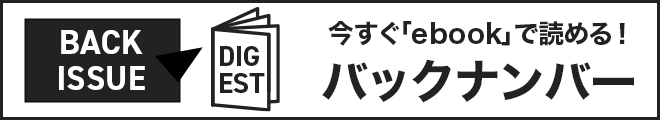最高裁が女性を「生物学上の女性」と判断性の多様化に逆風か
4月16日、最高裁は「生物学上の(biological)女性」と出生時は男性でしたがのちに自分の性は女性と認識する「トランス女性」が、法的に同等に扱われるべきかどうかを争った訴訟で、同等に扱われるべきではないとしました。最高裁が法律上の「女性」を「生物学上の女性」と定義したことで、大きな波紋が広がっています。
「女性=生物学上の女性」とする判断については「当たり前じゃないか」と思う人もいるかもしれません。でも、性についての考え方は多様化しています。生まれたときの性と心の性が異なるトランスジェンダー、あるいは特定の性に帰属意識を持たない人など、性の自己認識にはバリエーションがあります。こうした多様化に対応する施策、例えばジェンダー・ニュートラルなトイレの設置などが実施されてきましたが、最高裁の判断はこれまでの流れに逆行するようにも聞こえます。トランスジェンダーや性的少数派の人々を社会から阻害することにつながらないでしょうか。筆者は心配になりました。
司法闘争が始まったきっかけは2018年、スコットランド議会が公共部門の性別の均衡を確保するための法案を可決したときでした。この法律下での「女性」にはトランスジェンダーを含むとしたことに対し、女性団体「フォー・ウィメン・スコットランド」(FWS)が、生物学的な女性に限るべきだとして、提訴しました。訴訟は、年齢、人種、性別などによる差別を禁止する平等法(2010年)を巡って争われたのですが、この法律では女性の定義が明記されていないので、スコットランド自治政府はトランス女性も、女性として同法で保護されると主張していました。
スコットランド自治政府は、性の自己認識の多様化に対応する施策を積極的に実行してきたことで知られていますよね。2005年から出生証明書の性別を変更することが認められており、これを土台にして22年12月、変更に必要な「ジェンダー認定証明書」(GRC)の申請条件を簡易化する法案を可決させています。でも、英中央政府が正式な法制化を阻止。この法案と英国の平等法に含まれる保護規定の実践に矛盾が発生するという理由からだそうです。
最高裁の判決を受けて、政府に政策提言をする「平等・人権委員会」(EHRC)が臨時指針を発表しました。GRCの有無にかかわらず、男性として生まれてのちに女性として自己認識した人(トランス女性)は「生物学上の男性」であり、逆に女性として生まれてから男性として自己認識した人(トランス男性)は「生物学上の女性」であると明記しました。これによって職場、病院、店舗、レジャー施設、スポーツ組織、学校などの決まりに影響が出ることになる、とEHRCは指針の中で書いています。具体的には、職場ではいずれかの性に特化したトイレや更衣室の設置が義務化されるべき、と。公共空間となるレストランなどの施設では必ずしも義務ではないものの、女性専用のトイレがなく、どちらの性も利用できるトイレのみが提供されている場合、「間接的な差別になる」との解釈を示しました。スポーツについては「そのうち発表する」としましたが、学校のトイレも男女別々のトイレの設置を必須としています。
その後4月末にかけて、事態が急速に展開しました。陸上、自転車、水泳の各競技では以前からトランス女性が女子の試合に参加することが禁止されているのですが、今回の最高裁の判断を受けてスコットランドのフットボール協会が来年から、そしてイングランドのフットボール協会が6月からトランス女性が女性サッカーで競技することを認めないと発表したのです。イングランドとウェールズのクリケット協会は即時で参加を禁止することにしました。さまざまな性の自己認識を持つ人々を英国は受け入れてきたはずでした。トランス女性・男性の社会の中の位置付けについて、今後時間をかけてじっくりと議論する余地があるのではないでしょうか。
Biological Sex(生物学上の性)
生物学的・身体的な特徴に基づく性の区別。「出生時の性」と同義で使われる。染色体、性腺、テストステロン、エストロゲンなどのホルモン、性器などから判断するが、染色体やホルモンのパターンには多様性がある。性分化の過程で染色体、性腺、内性器や外性器が多くの人とは異なる型をとる「性分化疾患」(DSD)である人もいる。

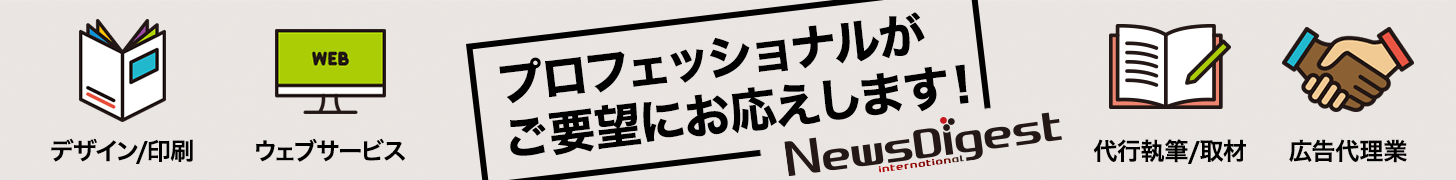

 パン柄トートバック販売中
パン柄トートバック販売中
 小林恭子 Ginko Kobayashi
在英ジャーナリスト。読売新聞の英字日刊紙「デイリー・ヨミウリ(現ジャパン・ニュース)」の記者・編集者を経て、2002年に来英。英国を始めとした欧州のメディア事情、政治、経済、社会現象を複数の媒体に寄稿。著書に
小林恭子 Ginko Kobayashi
在英ジャーナリスト。読売新聞の英字日刊紙「デイリー・ヨミウリ(現ジャパン・ニュース)」の記者・編集者を経て、2002年に来英。英国を始めとした欧州のメディア事情、政治、経済、社会現象を複数の媒体に寄稿。著書に